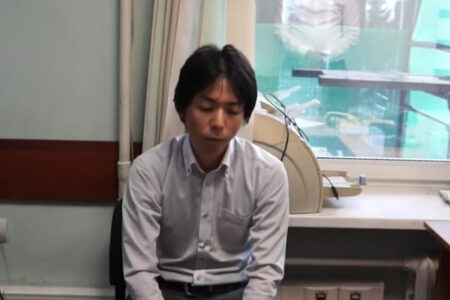人類の酒好きのルーツが判明!“飲める体質”と“酒を酌み交わす文化”をつくった名前のない行動

最新の研究によって、私たち人類が「お酒を楽しめる体質」を手に入れた進化の背景と、それが「酒を酌み交わす文化」につながった可能性が明らかになった。
ヒトの“飲める体質”はどこから?
2015年の研究によると、人類の祖先たちは木の上の果実だけではなく、熟して落下した果実(発酵果実)も食べていた。この習慣が、アルコールを分解する酵素(ADH4)の遺伝的な変化を引き起こし、アルコール代謝能力を40倍に向上させた可能性があると報告されている。
つまり、発酵果実を食べる習慣が、アルコールを分解する能力=“酒が飲める体質”につながったかもしれないということだ。
ただし、これは人類とアフリカの類人猿(チンパンジーやゴリラ)の共通祖先においてのこと。オランウータンなどアジアの類人猿にはアルコール分解酵素(ADH4)の変異はみられない(=アルコールを分解する能力が弱い)が、オランウータンが発酵果実を食べるかどうかの検証もされていなかった。
類人猿の食行動を調査
この行動の進化的意義に注目し、さらなる調査を行ったのが、アメリカのダートマス大学とスコットランドのセント・アンドルーズ大学の研究チームだ。
チームは、アフリカの類人猿であるチンパンジーとゴリラ、そしてアジアの類人猿であるオランウータンの野生での食行動を比較調査した。
その結果、チンパンジーやゴリラは定期的に地面に落ちた発酵果実を食べていたが、オランウータンにはその傾向が見られなかった。この違いは、オランウータンがアルコール分解能力を持たないという2015年の研究結果とも一致している。
祖先も酒を酌み交わしていた可能性
地面に落ちた発酵果実を食べる行動は、木の上で果物を奪い合う必要を減らし、競争を回避できる上に、大型の類人猿が木から落下するリスクを避けることができる。

さらに、仲間と分け合って発酵果実を食べる行動が、社会的な絆の形成にも関わっている可能性もあり、人類の「酒を酌み交わす」文化の原型かもしれない。
「スクランピング」という新語
この行動の進化的意義を明確にするため、研究チームは地面に落ちている熟した果物を好んで食べる行動を「スクランピング(scrumping)」という新語で呼ぶことを提唱した。
責任著者であるダートマス大学のネイサン・ドミニー教授は、「これまで木の果物と地面の果物を区別してこなかったため、行動の進化的意味が見過ごされてきた」と指摘している。
名前がなければ、どちらも“果物を食べる行動”として扱われ、科学的議論の対象になりにくいという。
また、共同責任著者であるセント・アンドルーズ大学のキャサリン・ホベイター教授は、「この夏、冷たいスクランピー(発酵リンゴ酒)を分け合うことは、私たちの類人猿の祖先が1000万年前にすでに行っていたかもしれない行動を反映しているのかもしれません」とコメントしている。(了)
参考:University of St Andrews「Scrumped fruit key to chimpanzee life and a major force of human evolution」(7/31)
参考:Dartmouth College「How ‘Scrumping’ Apes May Have Given Us a Taste for Alcohol」(8/4)